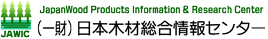わたしの机
大島つむぎさん(東京都)/木のある暮らしとわたし

先日、仕事で唐木細工の職人さんとお会いする機会があった。そのときに見せていただいた文箱を眺めているうちに、なんともいえない郷愁感におそわれた。どうしてだろう、文箱なんて持ったこともないのに……。家に帰り、写真を整理しているうちに思い当たった。やさしい角の丸み、深い色の木目……。そうだ!こどものころに使っていた机に似ていたのだ。
私が小学校に入るとき、買ってもらった机は木製だった。木目を活かした焦げ茶色で、ずっしりとした一枚板の天板と簡単な引き出しがついただけのシンプルなデザインであった。つくりも頑丈で、多分それは小学生が使うには贅沢すぎる品だったのだと思う。しかし、そんなことは6歳のこどもに分かるはずもない。当時、同級生が持っていた机は、ほとんどがスチール製でキャラクターのイラストがついたり、本棚や鉛筆削り、電気スタンドが一式になった賑やかなものだった。そんな机をみるたびに自分の無骨な机が恨めしく思えた。少しでもかわいくしようと、お菓子のおまけについていたシールを貼りまくったり、バラの模様の包装紙を敷き詰めたりして飾り付けたりしたものだ。
それでも家の中に自分の居場所があるというのは、うれしかった。個室など与えられない昭和40年代の住宅事情である。6畳間の一角に据えられたその机だけが自分の世界だった。多くの小学生がそうであるように、じっと机に向かって勉強するなどということはあまりしなかったが、ガキ大将にいじめられたり、親に叱られたりしたときには、よく机の下にもぐりこんだものだ。犬小屋の中でうずくまる子犬のように、狭い空間に座り込んでいると何かに守られているような気分になって、いつのまにか眠ってしまったりした。これがもしスチール製の机だったら、きっとオリにでも入ったような気分になっていたに違いない。
やがて中学生ぐらいになると、スチール製の机を使っていた友だちは、ガタが来たり、子供じみた装飾が恥ずかしくなったりして処分してしまう子も増えてきた。私の机はというと、色あせたシールの残骸や細かい傷はあったものの、つくり自体はびくともしていなかった。業者にお願いして磨きなおしてもらうと10年近く使ったとは思えないほど見事によみがえった。すると今度は、その大人っぽさに、まるで自分の“書斎”が出来たような晴れがましい気分になったものだ。
あいかわらず本来の目的である勉強に使われたことはほとんどなかったが、友だちとの交換日記や深夜のラジオにこっそり送ったリクエストカード、出さずじまいだったラブレター……。親や先生も知らない秘密を共有したその机とは、結局15年間つきあったことになる。
流行りのものではなく良質で長く使えるものを手入れしながらいつまでも持ち続けるという、私の価値観の原点はあの机によって作られたと言ってもよいだろう。私が家を出たあと、あるじのいなくなった机は人手に渡ってしまい、今ではどこで使われているのかもわからない。でも、あの机を与えてくれた両親に対する感謝の気持ちだけは、今でもしっかりと残り続けている。